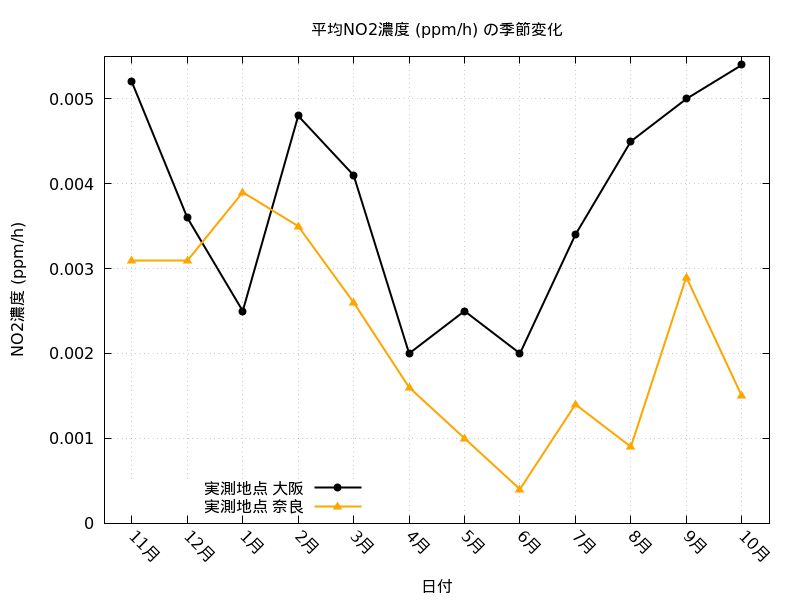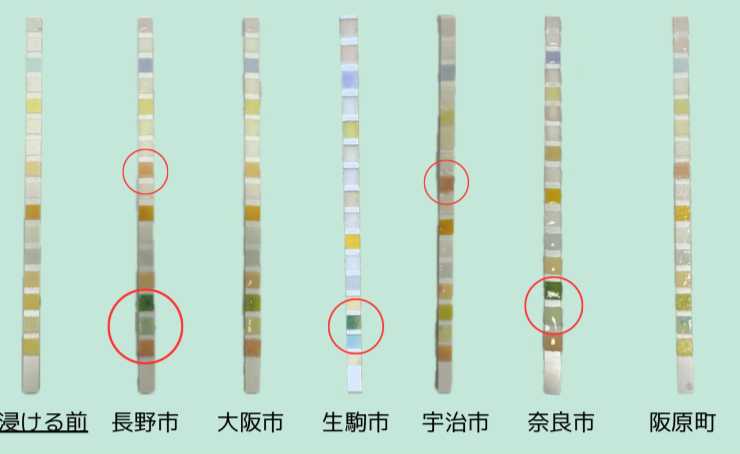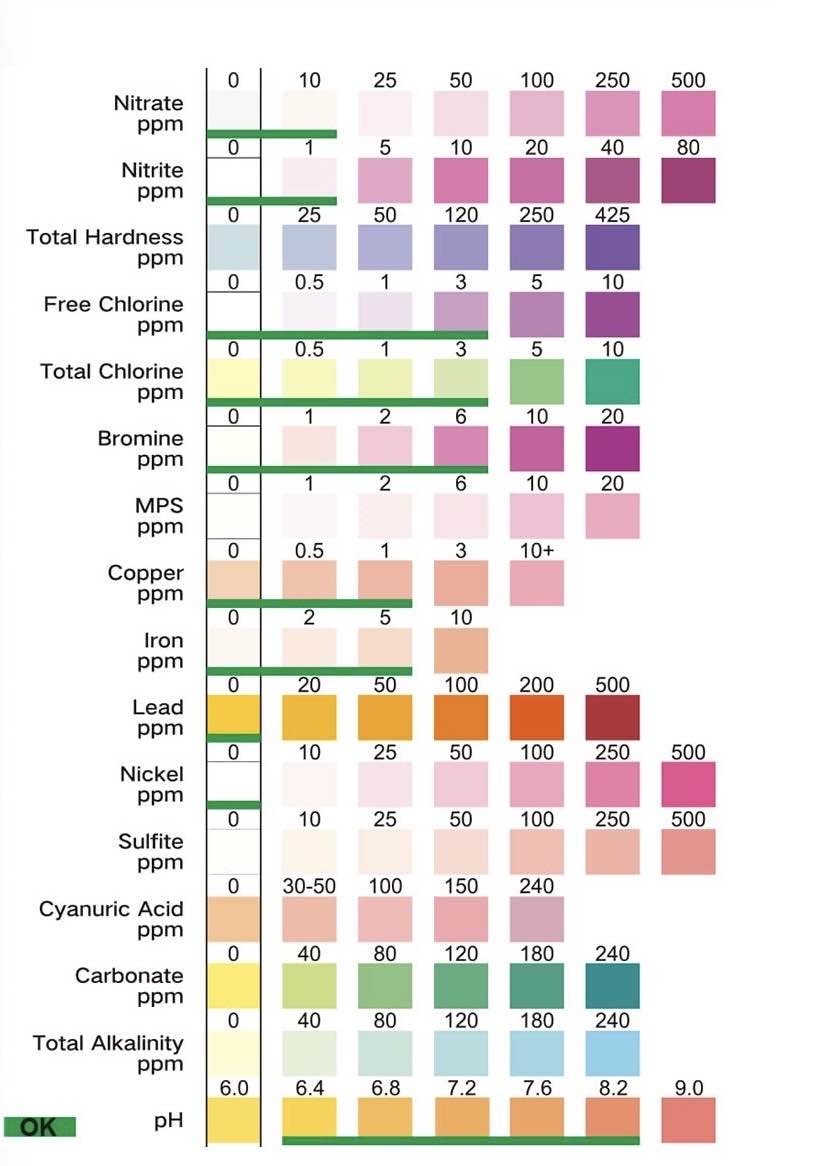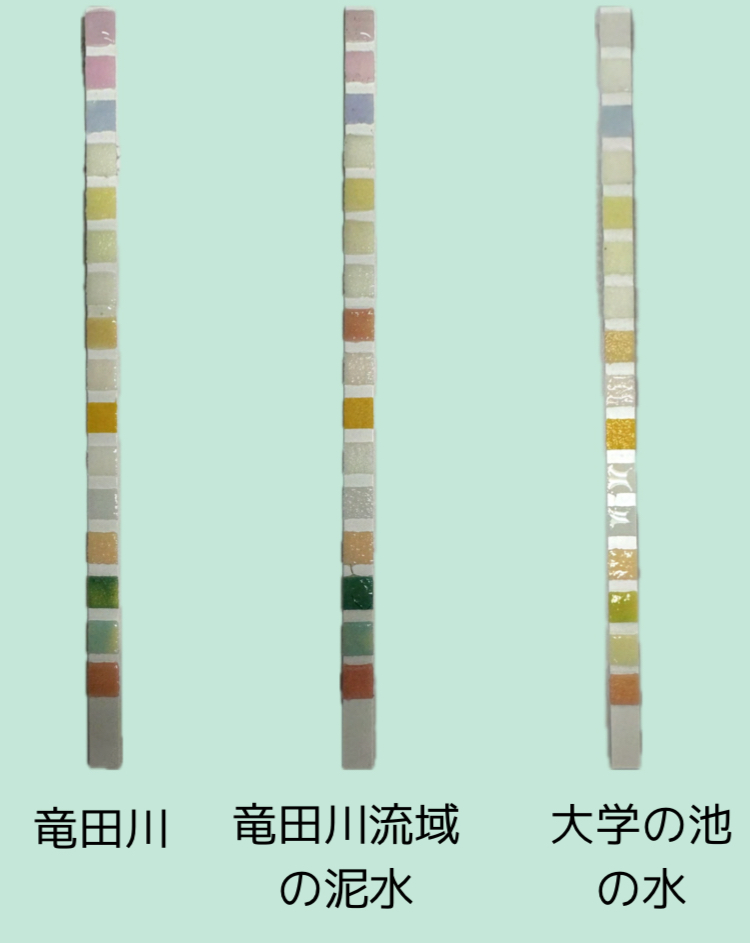自分でアプリを作ってみよう!
皆さんは、生成AIと聞くとどんなイメージを持ちますか?
便利、賢い、使っているのがバレたら先生に怒られそう…など様々な印象を持っていますよね。
AIは日に日に進化しています。
このような時代で我々に求められているものは、AIを疎ましく思うことではなく、AIを使いこなせる力です。
私達はアマゾンが提供しているアプリ生成AIを用いて、日常の問題を解決することができるアプリを作成しました。
是非、遊んでみてください!
また、こちらからアプリを生成することができます。
無料で出来ますので、興味のある方はチャレンジしてみてください!!
☆気になるテーマをクリックすると、アプリのページへ移動します☆
1.AIからのクイズに挑戦しよう!
・環境問題についてのクイズを出すように命令を書いたよ!
・クイズ形式にすることで難しい環境問題を楽しく学べるようにしたよ!
・みんなは何問正解できるかな!?
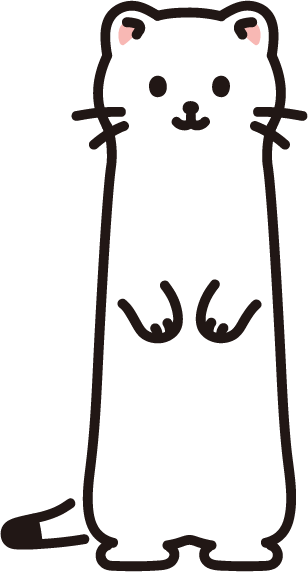
・今日の献立を入力すると、不足している栄養素を教えてくれるよ!
・ひとり暮らしだと栄養が偏りがちだから作ってみたよ!(辛いものばっかり食べちゃう^^)

・会話できるAIを作ってみたよ!
・自然な会話になるように会話例を作って、いろいろ学習させてみました!
・みんなもたくさん会話してみてね!
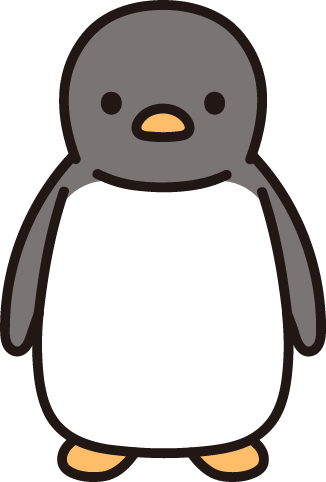
・2つの物語を入力するとその物語の特徴を捉えて、
誰も知らない新しい物語とそのイメージ画像を出してくれるよ!
・イマージ画像を出すことで、物語に親しみを持ちやすくしてみたよ!
・「シンデレラと桃太郎」みたいな組み合わせもOK!どんな物語になるんだろう~???

・世界の国の主要な環境問題について会話できるような命令を書いたよ!
・環境問題の例をAIに教えることで質問にも答えられるようにしてみたよ!
・自然な流れで会話できるようになっているから是非いっぱい話しかけてみてね(^^)